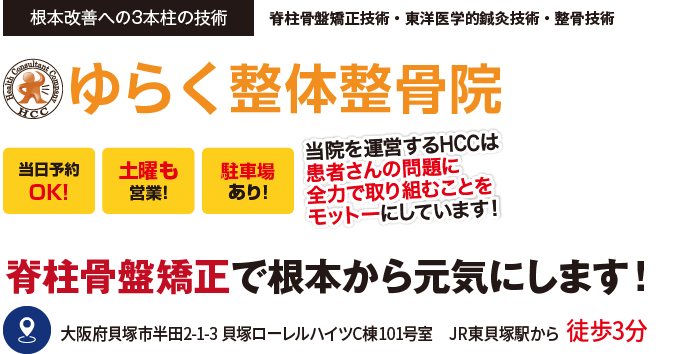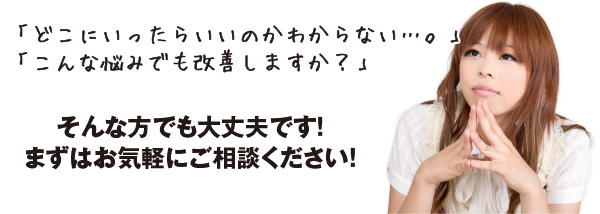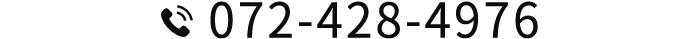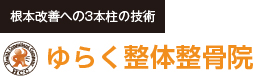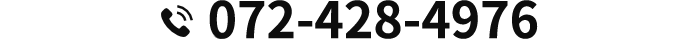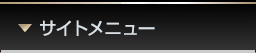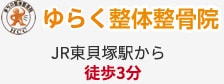限界を迎えた時だけが治療ですか?
2024.07.10
貝塚市にお住いの皆さんこんにちは!
整体に興味がある皆さん!
「カラダのケアせなあかんなぁ」と思いつつも、そのままにしていませんか?
自分の身体の事は二の次三の次になって負担ばかり溜め込んでいませんか?
そんな自分に飽きていませんか?
変えたいと思っていませんか?
体調を壊して限界と感じた時になってようやく治療をし始めると、自分が想定していない【予想外の時間】や【予想外の通院費】を支払うことになります。
そしてその治療が済めばまた負担を溜め込んでいく生活をしていませんか?
そしてまた体調を壊して限界と感じた時になってから予想外に時間と通院費を支払っていませんか?
これは【返済型思考】の人の考え方
マイナスを頑張ってゼロに戻すだけの人

一方【貯蓄型思考】の人の考え方は
ゼロにならないように常にプラスにしていて、そのために頑張っている人の事
同じ「頑張り」なのになんか全然違うよね
体調を崩した状態だと何事も全力って出せません。。。
例えば、腰痛いなか好きな人とデートして上手くいきますか?
首痛い中好きな人とデートして楽しいですか?
頭痛の中仕事して効率いいですか?
頭痛の中育児して効率良いですか?
常に全力を出せるように健康をキープすることがどれだけだいじなのか分かっていてそのための行動が出来ている人
これが【貯蓄型思考】の人
健康をキープするために
【予想内の時間と予想内の通院費】を支払う生活に変えてみませんか?
残念ながら健康は誰かから与えられるものではありません
自分が自分に与えてあげる事しかできません
貯蓄型思考の人はすぐにご予約を♪
返済型思考の人は限界を感じた時にご予約を♪
ご予約はこちらから
アクセスはコチラをチェック
インスタグラム
フェイスブック
エキテン
#貝塚市 #整骨院 #整体 #治療 #腰痛 #骨盤矯正 #姿勢改善 #健康
毒出し整体の秘密
2024.07.02
身体の解毒器官の働きは万全ですか?

肝臓は人体における最大の内臓であり、代謝や解毒、ミネラルやビタミンや血液の貯蔵庫としても
働く重要なところです。
日常のストレスや怒り、またはアルコール類や添加物など様々な処理に働き続けてくれる肝臓を
東洋医学的にその肝臓の気を高めてくれるツボの存在があるとしたら知っておきたくないですか?
ちょっと自分自身でマッサージすることにも使えますね!
〇〇整体整骨院で受けることができる毒出し整体では
この肝臓の気を高めることができる
「大敦」(だいとん)」

写真の赤丸の場所で、足の親指の爪の外側の角にあるツボです。
肝臓にストレスがかかって働きが悪くなっていると、解毒機能が低下し血中に毒素が
流れてしまうそんなことの改善に働きかけることで肝臓が元気になり働きがよくなる秘孔です。
しかも、耳鳴りや難聴にも効果ありなんです。
ゆらく整体整骨院では
ここをしっかりと網羅した毒出し整体になっています。
病気に変わる前にちょっとした体の疲れとともに内臓の働きを高めるような施術があれば便利です。
病気になってから痛みやら休養やらのリスクを背負って処方箋をもらうのと
病気になる前にリスクを背負わずにケアすることができる予防線なら
どちらがいいでしょうか?

処方箋は薬屋さんしか儲かりません^^;
予約はコチラ
Google情報 ゆらく整体整骨院
インスタ ゆらく整体整骨院
Facebook ゆらく整体整骨院
エキテン ゆらく整体整骨院
#腰痛 #毒出し整体 #吸い玉 #足つぼ
#カッピング #骨盤矯正 #ゆらく整体整骨院
#ツボ #肝臓機能 #デトックス #鍼灸治療
毒出し整体
2024.06.30
こんにちは!
ゆらく整体整骨院です。
季節の移り変わりは早いものでもうすぐ夏はやってきますね!
大気や気候の変化とともに体調も急激に変化します。
突然の体調不良の予防や健康維持のために我々は「毒出し」という整体法に辿り着きました!
体に蓄積した毒素を体外に排出すれば新しい新鮮な血液が全身を巡り、ホルモンバランスや自律神経の調整にもつながります。
今回は日頃から毒素を溜めない生活習慣についてお話ししたいと思います。
まず、体内に蓄積した毒素を取り除くには排泄機能を使うことです。
排泄機能として排尿に関係する腎臓、排便に関係する腸が正常に機能することが大切です。
そのために共通して重要になるのが水分です。
1日の水分摂取量としての目安としては食事から1リットル、飲み物から1.5リットルの合計2.5リットルは理想です。
ただし、飲みものからの1.5リットルの水は一度に飲んでも体が吸収できません。
逆に胃に負担をかけてしまうこととなるので、1回の摂取量をコップ1杯分とし何回かに分けて摂取すると体に負担がかかりません。
水を使ったデトックス法は飲むだけではありません。
お風呂でのシャワーも活用できます。
老廃物を集める機関としてリンパ節があります。このリンパ節を刺激し、リンパの流れをよくすることも老廃物を排除する働きになります。
まず温かいシャワーを鎖骨付近にあて、続いて足のつま先から膝、太もも、股関節へ向かってシャワーを当てます。
次にての指先から手首、肘、脇の下にゆっくりシャワーを当て、最後にお臍を中心に時計まわりにシャワーを当ててお腹を刺激します。
その他にもお風呂でできるデトックス法として38度から40度のお湯で半身浴をすることもおすすめです。
新陳代謝が上がり発汗により老廃物を排出することができます。
この様に内臓の働きやリンパの流れをよくすることが毒素を溜めない生活習慣として大事です。

これらの作用として自律神経が大きく関係します。
腎臓は特に自律神経の影響を受けやすいので自律神経神経を調整できる鍼灸治療や東洋医学が毒素が溜まりにくい体質作りには必要です。
当院の「毒出し整体」は東洋医学で太古から使われている吸い玉と浮腫やむくみとして毒素蓄積が現れやすい足部の足底マッサージを併用したどんどん毒素を排出するための施術です。

最近いくら寝ても眠たい、やる気が全く出ないという方!
毒素に体を蝕まれている可能性がありますね。
ぜひ毒出し整体をご体験なさってください!
毒だし整体はこちら!
〒597-0033 大阪府貝塚市半田2丁目1−3 ゆらく整体整骨院
場所はこちら!
貝塚市半田のゆらく整体整骨院が解説する、吸い玉で期待される効果
2024.06.17
こんにちは!
貝塚市半田にある、ゆらく整体整骨院の森井です!
今日は吸玉についてお話しますね☆
吸玉の歴史は古く、西欧では紀元前2千年頃にはすでに行われていたそうです
日本では、江戸時代や明治時代から盛んに行われていた民間療法です。
現代では、専用のカップを身体に吸いつけて、カップ内を真空状態にすることで、皮膚や表層の筋肉を引き上げて外すという手順で行われることが多いです。

そんな長い歴史のある吸玉には、多くの効能があります。多くの効能があるから、古くから伝えられてきたのでしょう!
まず一つに、血流改善!
真空の力で吸い上げられた瘀血と呼ばれる、ドロドロとした滞った血液を吸い上げて、カップを外した際に止まっていた血液が流れだし、血液循環の改善が促進されます。

カップを外した箇所に赤、紫の色がでて、滞っている方ほど色が濃くでます。
吸玉の跡は1週間ほどで自然と消えていくのでご安心下さい。
吸玉をしていくことで、血流が改善していけば、色が薄くなり、吸玉の跡も消えやすくなっていきますよ!
吸玉をした場所の筋肉自体の血行不良によるコリ、痛みの症状の緩和も期待されます。
慢性的な肩、腰のコリや痛みがある方は吸玉治療で改善の可能性大です。
他にも、血流が良くなることで、
*自律神経の作用の正常化による睡眠改善、ストレス解消、便秘改善
*リンパの流れも良くなることで、デトックス効果、むくみの改善
*毒素が体内から排出されやすくなり、ダイエット効果の向上
など、吸玉による効果は良いことずくめです^_^
ゆらく整体整骨院では、今週6/19、21、22と吸玉の無料体験を行っています!
慢性的な肩こり、腰痛や上記の症状でお悩みの方は吸玉で血流改善してみませんか?
#吸い玉 #カッピング #デトックス #ダイエット #自律神経 #肩こり #腰痛
初めての方の予約はコチラ
ゆらく整体整骨院
〒597-0033 大阪府貝塚市半田2-1-3
店舗MAPはコチラ
インスタグラム ゆらく整体整骨院
フェイスブック ゆらく整体整骨院
エキテン ゆらく整体整骨院
骨粗鬆症予防
2022.01.11
こんにちは!元気モリモリ森井です!
今回は、骨粗鬆症についてお話しさせてもらいます。
みなさんの体を当たり前のように支えてくれている骨ですが、骨量は男女ともに30歳頃がピークに達するといわれております。
また男性は女性よりも骨量が多いです。
骨は常に吸収と形成を繰り返しているのですが、通常ではそのバランスは均等に保たれているのですが、骨を形成する骨芽細胞と骨を吸収する破骨細胞の調節バランスが崩れると、骨は次第に脆くなってしまいます。
バランスが崩れる原因に、副甲状腺ホルモンやカルシトニン、エストロゲン、ビタミンDなどが関わってきます。
骨粗鬆症により、起こりやすい骨折としてあげられているのがあります。
①橈骨遠位端
②脊椎の圧迫
③大腿骨頸部
④大転子
この中でも最も起こりやすいのは、脊椎の圧迫骨折です。
経験上、高齢者の日常生活における転倒によるもので、上記のような骨折をされる方が多いです。
転倒して手を着いたとき、尻もちを着いた時など、軽く転けただけなのに…と思うような転倒で起こりうるので転倒しないように注意が必要です。
女性は骨粗鬆症の内95%以上、男性は骨粗鬆症の内80%が原発性であります。
ほとんどの症例で、女性は閉経後、男性は高齢者で起こります。
多くの原因が、男女ともに性腺機能不全といわれています。
その他の因子としては、カルシウム摂取不足、ビタミンDの低値、副甲状腺機能亢進症などがあります。
ごくわずかですが、青年期の骨成長の時期にカルシウム摂取が不十分で、骨量がピークに達しないケースもあります。
ですから、一番は高齢者が要注意です。
ただし、男女によって年齢差はあると考えていいと思います。
女性の閉経年齢は、人によって違いがあるので早い方なら40〜50代から注意が必要です。
◯骨粗鬆症対策 その1
上記のことをしっかりと分かった上で、自分が骨粗鬆症になっていないか検査をすることも重要です。
検査方法としては、骨密度検査があります。
痛みが全くなく、数秒の時間しかかからない為、非常に手軽にできる検査です。
また、骨形成を促進させる服用薬もありますので、こちらも簡単に予防できる方法です。
当院で提携しているクリニックでは、こちらの服用薬の処方や検査を受けることができますので、お悩みの方は一度受診してみて下さい。
◯骨粗鬆症対策 その2
その他にも予防するためには、普段の食事から変えていくことです。
骨密度を低下させないための食事
ポイントは、カルシウム、ビタミンDです!
カルシウムを多く含む食材
牛乳、乳製品、小魚、干しエビ、小松菜、ちんげん菜、大豆製品などです。
ビタミンDを多く含む食材
サケ、ウナギ、サンマ、シイタケ、キクラゲ、卵などです。
逆に控えてもらいたい物は
スナック菓子、インスタント食品、アルコール、カフェイン、タバコなどです。
こういった食事に気をつけることで体の中から改善していきましょう!
◯骨粗鬆症対策 その3
実は、日光浴がいいんです!
昔からお日さんに当たりなさいとかよく言われていますが、それは本当なんです!
日光浴をすることで、カルシウムの吸収を助けてくれるビタミンDが体内で作られます。
浴びすぎると皮膚のダメージに繋がるので、30分ぐらいにしましょう。
吸玉
2021.11.30
こんにちは!
元気モリモリ森井です!
今回は吸玉について投稿します!
吸玉はみなさんご存知ですか?
吸玉の歴史は古く、数千年も前から使われていたとも言われています。
しかも東洋側だけでなく、西洋側にもその技術は広まっていきました。
吸玉はカッピングとも呼ばれ、旧式のものは瓶のカップの中にアルコール綿花を燃やしたものをサッと入れて中の空気を陰圧にした状態で、背中などの施術部位に被せます。
そうすると皮膚や筋肉がキューッと吸い上がってくるので、その力により筋肉中に流れている血液も同時に吸い上がってきます。
最新のものでは、プラスチックのカップでポンプ式の要領で吸い上げるものがあります。
旧式では火を扱うため技術的に鍛錬が必要で、施術者によって技量に差が出てしまいますが、最新のものでは、ポンプを引っ張る回数で強さを調節できるため、非常に簡単かつ技量に差が出ないようになっています。
ではここで吸玉の実際の写真をみて頂きます。

これが最新のポンプ式の吸玉です。
この方は、肩こりが何十年も続いており、ひどい時は腕や首、頭痛がするなどの症状で困っています。
身体の状態としては、肩甲骨周りの筋肉の緊張が非常に強く、腕を上げたり動かす時に肩甲骨の動きが悪くなってしまっています。
ただ座っているだけなのに、なぜか肩がだんだんしんどくなってくる。
夜寝て朝目が覚めると、なぜか肩周りがガチガチで寝たのに疲れている感じがする。
この様な症状がある方は、かなり肩甲骨周りの状態が悪いといえます。
吸玉をつけると、身体の表面に悪い血流が集まってきます。
この血流は、東洋医学的に瘀血と呼ばれるものです。
身体の中の毒素、疲れ成分の乳酸、水分不足によって血がドロドロ、筋肉の挫傷によって筋内部に内出血が起こっている場合など、理由はさまざまあります。
吸玉の色と日常生活での動作、仕事での動作、食生活など総合的に考えて、身体の状態が悪くなっている理由を探していきます。
吸玉の色として良い状態から順に、肌色に近い色→薄ピンク→薄むらさき→濃むらさき→ドス黒 がかなり悪い状態となっています。
この色は、早くて3日〜遅いと10日ほど型が残ります。
血流が悪い人ほど、型が消えるのもおそくなりますし、色も濃くなるのが特徴です。
こちらが実際に吸玉を外した後の状態です。

背中全体的に非常に色が濃むらさきになっています。
仕事上かなり重たい荷物を持たれるので、背部の筋肉の緊張が強くなってしまっていました。
側湾症
2021.11.28
こんにちは!
元気モリモリ森井です!
体が痛くなったときの原因って、気になりませんか?
当院に来られる患者様の中でも痛みが取れたからって治療をやめてしまう方がおられます。
たしかに痛みはとれて体は楽になったかもしれません。
仕事や趣味、日常生活で困ることもなくなると治療の必要性を感じなくなるのでしょうか。
痛みがとれて治療をやめてしまうと、また痛くなったなんてことはありませんか?
痛みが取れるということは、痛めてしまった筋肉などの組織が修復されたということですが、また痛くなるということは、他にも原因があるということです。
この原因を改善しなければ本当の意味でよくなったとは言えません。
こちらの写真は実際の患者様の姿勢の写真です。

肩の高さや頭の位置を線で結ぶとよくわかりますが、かなり左右で高さがズレています。
ここまでのズレがあるのは、骨盤を土台としている背骨に歪みが起こっているからです。
この方は仕事で重たいものをもつことが多く、持っている姿勢がこのような歪んだ姿勢を引き起こしていました。
背部の筋肉の緊張が左右で違っており、片方の背中だけ痛くなっているのが特徴的です。
背部の筋肉が緊張してくることで、夜寝る際の寝つきに影響を及ぼして不眠症の症状も出ていました。
そのため、頭痛や眼精疲労、肩のこりなど、さまざまな症状が誘発されて、仕事の効率も悪くなるため患者様自身とても悩まれておりました。
これらの原因は、先天的な場合もありますが、多くの場合が日常生活における姿勢の悪さからくるものです。
例えば、車の運転をする仕事の人です。
運転中の姿勢が原因で、片肘をついて運転していたり、斜めに座っていたりすると背骨の傾きが知らず知らずのうちに定着してしまいます。しかも長距離ドライバーとなると、車の座席を倒して横になって仮眠したりするので、余計姿勢は悪い状態になってしまいます。
この様に自分の姿勢がわるくなっていると知らない方が多く、姿勢の写真を見てびっくりされる肩も多く、写真をみて初めて体の悪さに気づく方もおられます。
姿勢の悪さが分かれば、治療するポイントも明確になります。
毎回治療後の写真をとることで、治療を重ねていく中で姿勢が少しずつ良くなっているのが目で見て変化を確認することができます。
これらの治療を繰り返しおこなうメリットや感覚的に身体の軽さ、痛みの軽減など、症状の改善を感じることで治療の必要性を実感できてきます。